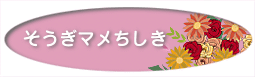
葬儀豆知識 お葬式は人生の最後を送る厳粛な儀式です。遺族にとっても、会葬者としても深い悲しみの気持ちを正しく表現するのがマナーであります。 これ等の形式は古くからの習慣に従って行われ、それぞれの地域、宗教、宗旨によっても大きく異なることがあります。 このホームページは、ご会葬者の方々の為にごく一般的な常識をまとめてあります。
- 通夜 昔は文字通り夜通し行われたもので、故人のご遺体の傍らで別れを惜しむのが本来の姿で、「夜伽」とも云います。現在では午後6時〜7時ごろ始まり、9時〜10時ごろまでというのが一般的です。できれば読経の始まる前に伺いましょう。焼香の後、僧侶の退席を目安に辞去してもかまいません。
- 通夜での服装 儀式ではありませんので正装する必要はありません。地味なスーツやワンピースなどで装うのが心遣いです。アクセサリー類は原則としてしない方がよろしい。
- 通夜の席次 特に定まった席次というのはありませんが、一般には祭壇に向って右奥から喪主、遺族、近親者。左側奥より葬儀委員長、世話役代表、近親者、一般知人、友人、会社関係と云うように血縁の順に座るのが普通です。弔問客は先着順にどうぞ。
- 通夜の作法 受付で名前を記入するか名刺を渡し香典を差し出します。受付のない場合は祭壇に供えますが、このとき金封の表書きが祭壇から正面に見えるように置きます。祭壇のある部屋に入った時は先客に軽く一礼のうえ、静かに入室そして遺族に短くお悔みを述べますが、弔問をすませている時は丁寧に一礼するだけにし、祭壇の前へ進み焼香を致します。告別式に参列できず通夜だけに出席した場合、近親者か世話人にその旨を伝えおわびしておきましょう。帰る前にもう一度祭壇の前へ進み合掌するのがより丁寧なマナーです。
- お悔みの挨拶 心さえこもっていれば言葉につまって深く一礼するだけでも十分に気持ちは通じます。遺族の気持ちを察して「このたびはとんだことで・・・心よりお悔み申し上げます。」程度に短く切り上げましょう。
- 焼香の作法 (数珠は焼香時には欠かせない物です。必ず持参いたしましょう)
焼香は死者の霊を供養し、その香気によって霊前を清める為に香を焚くことです。通夜や法事では線香を、葬儀や告別式では抹香を使うのが一般的です。
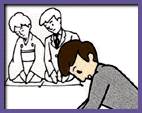 (1)まず次の人に会釈して祭壇前の遺族の並ぶ末席まで進み、僧侶と遺族に向って一礼します。
(1)まず次の人に会釈して祭壇前の遺族の並ぶ末席まで進み、僧侶と遺族に向って一礼します。
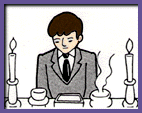 (2)焼香のできる位置まで進み位牌と戒名と故人の写真を見て一礼します。 ※祭壇の前に座ぶとんが置いてあっても、これは僧侶のために用意されたもので敷かないのが礼儀です。
座ぶとんを脇によけてから、一礼して焼香します。 焼香後、遺族に一礼して座ぶとんを元の位置に戻します。
(2)焼香のできる位置まで進み位牌と戒名と故人の写真を見て一礼します。 ※祭壇の前に座ぶとんが置いてあっても、これは僧侶のために用意されたもので敷かないのが礼儀です。
座ぶとんを脇によけてから、一礼して焼香します。 焼香後、遺族に一礼して座ぶとんを元の位置に戻します。
 (3)次に香箱から右手の親指、人差し指、中指の3指で香を少量つまみ、香炉の中に静かに落とします。
焼香の回数などの作法は宗派・地域により異なります。(1回〜3回)参列者の多い時は1回にしてもかまいません。
(3)次に香箱から右手の親指、人差し指、中指の3指で香を少量つまみ、香炉の中に静かに落とします。
焼香の回数などの作法は宗派・地域により異なります。(1回〜3回)参列者の多い時は1回にしてもかまいません。

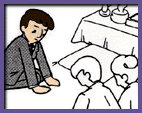
(4)焼香のあと合掌し、深く一礼をしてから、やや下がり、左右に一礼、右まわりして席に戻ります。 立席の場合もほぼ上に準じて行います。一番大切な事は心から故人のやすらぎを願うことです。 - 香典 香典本来の目的は人の死と云う不幸に際してお互いに助け合う精神から来ております。通夜に出席するときには通夜に、通夜に出席しない場合は告別式に持っていくのがふつうです。
- 香典の渡し方 香典を服のポケットやハンドバッグから直接出すのは失礼にあたります。弔辞用のふくさか、地味な色の風呂敷に包んで持参すると良いでしょう。受付があれば芳名録に記入を済ませ香典をふくさから出して相手の方へ向けて差し出します。受付がない場合は祭壇に進み礼拝する時に自分の姓名が相手側になるよう、盆又は机の上におきます。
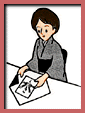
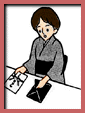
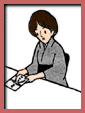 123
123 - 香典などの表書きの知識 (仏式)
御霊前・・・葬儀で死者の霊前へ供える金品に一般的です。(浄土真宗では使いません)
御香奠・・・故人が目上の場合、霊前に供えるのに適当です。
御香典・・・御香奠と同じ(目上の人へは避けた方が良い)
御香華料 御香料・・・香華を手向けるという意味で故人が直属の上司の場合。
御悔・・・葬儀の前に霊に供える金品に。
御供・・・供花・花環・盛り篭等の品物を供える時、法要時の金封にも。
御佛前・・・法要で仏前に供える金品に。 - 神式での金封の表書き
御霊前・・・神式の葬儀で霊前に供える金品に。
御神前 御玉串料 御榊料・・・神式葬儀の他、神式行事一般に。 - のし袋の種類
仏式:黒、白、銀水引の結び切り、中身の金額に合わせてのし袋を撰びましょう。 品物の場合は黒、白、銀水引印刷ののし紙を使用します。
神式:黒、白、銀水引の結び切り、蓮の絵模様入りは使いません。 ※法要には黒、白、銀、黄、白水引の結び切りを使用します。
おき ものがたり || おそうしき || そうぎマメちしき || せいぜんよやく || ぶつだんばなし || おはかばなし
TOP