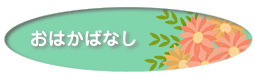
●お墓について
- いつ建立するか 仏壇と同様「四十九日」や「百か日」といったぐあいに法要を一つの区切りに求める。一般的には一周忌に立てる方が多い。また立て替え、お墓の整理も法要、あるいはお盆、彼岸といった仏行事の月にするのが一般的である。
- 墓石の種類 墓石として用いられる材料は、殆どが御影石(花崗岩)である。最近では外材が6割以上占めている。強度についても、国内産もあまり変わらなく、種類も豊富で価格についても安価である。国産では、北木石(岡山県)大島(愛媛県)庵治石(香川県)が代表的である。
- 墓石の向き お墓を建てる向きは、特に決まりはないが一般的には南向き、あるいは東向きが良いとされているが、立地的な問題もあり北向のお墓も多く、ようは祭る側の気持ちの問題である。
- 墓石の大きさ もっともポピュラーな和型墓碑の標準的な大きさは、七寸角(棹石の横幅が21センチ)、八寸角(同24センチ)など、これに合わせて棹石の高さ、台石の幅が決まってくる。 参考: 墓石の構造は上から「棹石」「上台」「下台」、下台の前に「水鉢」「花立」、そして水鉢に家紋を、下台には納骨穴がありその台のしたにカロート(納骨棺)がある。
- 墓地の面積 墓地の広さについては、一般的に90センチ角を一霊地または一聖地と言い、畳半畳が一霊地、一畳が二霊地といった具合に墓地の広さを表します。そして、境界をはっきりとするために、境界石をするのが望ましいでしょう。
- お墓の立替について 古いお墓を立て替えたい、古いお墓がたくさんあるので整理したい、このように先祖を十分にうやまいたいという気持ちが生じたとき「お墓をさわると縁起が悪い」などと、二の足を踏むことがあるが、われわれの家も傷んだり、老朽が進むと立て替えするように、先祖の家も同じである。ただし、そのときには心をこめて先祖に対する鎮魂の意味もこめて、供養の儀式をとりおこなうことだ。
- 墓地にあったお墓を建てる どのくらいの大きさのお墓を建てたらよいか、迷われる方が多いのですが和歌山では七寸型が多く、その墓所にあった大きさが望ましいでしょう。周りの状況にあわすのも良いでしょう。ようはお墓の大きさも重要であるが、最大の目的はお参りやお守りを大事にしたいものである。
- 開眼式 開眼供養は、「魂入れ」「性根入れ」ともいわれているように、新しい墓石が完成したとき、僧侶に頼んで墓としての機能を持たせる儀式である。墓前には、海の幸、山の幸、里の幸、お酒、洗い米、塩などお供えし、僧侶の進行で儀式を執り行う。このときには納骨供養も同時に執り行う場合が一般的である。僧侶へのお礼は、「お布施」または「開眼御礼」として包むことになっている。浄土真宗ではこの儀式を建碑式といい、表書きも「建碑式御礼」とします。
おき ものがたり || おそうしき || そうぎマメちしき || せいぜんよやく || ぶつだんばなし || おはかばなし
TOP